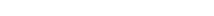更新情報
2025年7月 茶況_No.416
産地情報
令和7年7月28日
茶 況
二番茶の摘採が終了した茶園では防除や施肥などの管理作業が進められています。連日の猛暑が続き日中を避けて朝夕の涼しい時間帯に作業を続けています。この頃は30度超は当たり前となり真夏日は続きます。昨年は底なし相場から二番茶は採算割となり生産を中止する工場や、将来の見通しが立たない状況から廃業を決める工場が続出しましたが、今年は真逆の相場展開となり、ドリンク原料の争奪戦により価格は前年比2倍の異例な展開で終了しました。長引く茶価低迷から一転、20年ぶりの高値水準に急反発しました。
産地問屋は仕入した二番茶の仕上と保管作業を進めていますが、猛暑により工場内の温度も上がり、こまめに水分補給と小休止を取りながら作業を進めています。二番茶の高騰により「この相場では収支が合わない」と途中で仕入を中断した問屋もあり中小問屋は岐路に立っています。急須でで入れる煎茶を主に扱う問屋は、売上減により廃業も視野に厳しい局面を迎えています。
消費地の商店街では、暑さを避けるために日中の人通りはまばらです。来店して頂いたお客さまに冷茶による接客とコミュニケーションを欠かさず「おもてなし」を心掛けています。そして、「水出し煎茶」や「冷茶」の美味しい作り方を説明したり、外出時には「緑茶マイボトル」をお奨めします。「この店に来て良かった」と満足していただけるように努力しますが、物価高に伴う節約志向が強まり買い控えに直面しています。売上減により閉店するお店も増えています。
今年の茶況を総括しますと、ドリンク原料の争奪戦、海外の「Matcha」ブームによる碾茶価格の高騰と抹茶原料不足、現在の消費動向が顕著に表れました。一番茶は茶園の一部を碾茶用の被覆茶園に転換したことなどから煎茶の荷口が品薄気味で平均価格は2割強高くなり2千円台で終了しました。生産者は煎茶の摘採と碾茶の被覆作業が重なったりして煎茶と碾茶の両立の難しさを改善する必要もあります。また、被覆開始時期で収量の増減がありますので、適期の見極めも今後の課題です。有機茶や碾茶への切り替えが進み、出回りが減った一番茶の価格が維持された形です。
二番茶は、一番茶が2千円台で終わりましたので、この流れを受け昨年より500円程高い価格で始まり、碾茶に移行した茶園もあり日々の上場数量が増えないことにより、中盤以降はペットボトル原料確保の争奪戦となり平均価格は昨年比2倍の「狂乱相場」で終了しました。急須で入れる上級茶の価格は低迷し、ペットボトル原料の二番茶と秋冬番茶は急騰し、Matcha原料の碾茶価格も安定しています。そして、9月下旬から始まる「秋冬番茶」も過去にない相場展開になるとの観測が広がっています。農業従事者の高齢化と後継者不足により担い手が減り続けて農業の危機を迎えていますが「令和の米騒動」「二番茶の急騰」などで明るい兆しが見え始めた矢先に、日米関税交渉の結果として米国トランプ大統領の要求により米・大豆・トウモロコシなどの農産物を大幅に輸入拡大する事態となりました。日本の農業に再び暗雲が漂い始めましたが、この先何があるか分かりません。
ゆく河の流れは絶えずして、しかも元の水にあらず
どうなる日本。今回の参院選で自公政権が大敗し、歴史的な転換点を迎えました。石破首相の指導力と自民党政権の担当能力にNOと疑問符が突き付けられました。スピード感を欠く物価高対策、民意が反映されていない社会を変えることができない政治、方針が二転三転して不満と不信が溜まり有権者は新しい風を期待しました。その結果、自公政権は衆参両院で過半数を割り、多党政治へと移行しますので決めたいことが決まらない新しい日本政治の転換点を迎えます。法案では必ず野党に協力を求めることが必須となり、野党がまとまらないと政治が動かない状況となります。
日本の将来を考える枠組みを長期的な視野で考える時が来ています。今回の選挙では批判票を取り込んで参政党が大躍進しました。新聞やテレビを見ない若い人にユーチューブやSNSで動画を発信してユーザーと深いつながりや強い絆を構築し、一度検索したユーザーに関心があると考えられる投稿を繰り返し表示するように最適化されています。アマゾンで商品を一度検索すれば次から次へと同じ商品の情報が送られてくるようなものです。「日本人ファースト」の参政党は反グローバリズムの右派ですが世界的な潮流を上手くつかんで支持を大きく伸ばしました。二大政党の時代から多党化の時代へ、新聞・テレビの時代からユーチューブ・SNSの時代へ、グローバリズムの時代から反グローバリズムの時代へ、時代は大きく流れています。
かつて「小売りの王様」として隆盛を誇った百貨店が次々とその灯を消しています。昔は百貨店は身近なお出かけの場所でした。休日には家族で出掛けて洋服や日用品を買いました。友人やカップルで連れ立って流行の服や雑貨を見て回り、お茶をするのが楽しみな場所でした。35年前に9兆7千億円あった全国百貨店の売上は、現在は5兆5千億円まで減少しています。店舗数は311店舗から半減しました。郊外型の大型ショッピングセンターやネット販売が台頭し、百貨店は消費の変化に十分な対応ができていませんでした。しかし、名古屋高島屋・高島屋新宿店・新宿伊勢丹・銀座三越などは高級ブランド店を揃えて富裕層や訪日外国人の需要を取り込み変化に対応して地域一番店の座を強固にしています。百貨店が誕生したのは1904年、呉服店が時代の変化に応じて転業したのが始まりです。小売業は「変化対応業」とも言われますが、社会の需要を敏感にくみ取り変化に対応した新たな市場を開拓することは必須課題です。選挙の情報収集も新聞・テレビからユーチューブ・SNSに変わってきました、新聞発行部数は半分になり販売店の廃業が増加しています、時代の変化とともに様々な業種が衰退し、色々な業種が新興しています。農業も高齢化や後継者不足による廃業から担い手が減り続けています。お米の生産者は10年で4割減り「令和の米騒動」に発展しました。茶業界もペットボトル緑茶が消費の主流となり今年の二番茶は昨年の2倍に急騰しペットボトル原料を扱う問屋は原料確保に奔走しました。海外Matchaブームを受けて国内でも抹茶ブームに火が付きました。店頭では「一人一個まで」と販売数量を制限する事態となっています。原料の碾茶の相場も高騰して前年比2~3倍の値で落札されることもあり「今年は狂乱相場です」の声まで出ています。ペットボトル緑茶と抹茶は元気がいいのに、急須でお茶を飲む習慣の衰退は加速し、上級煎茶の相場は下がり続けています。静岡県では消費が低迷する煎茶の魅力を発信して「日本茶ファースト」で業界を盛り上げたいと企画しますが、時代の流れに抗えないのが現実です。「ゆく河の流れは絶えずして、しかも元の水にあらず。淀みに浮かぶうたかたは、かつ消えかつ結びて久しく止まりたるためしなし。」鎌倉時代に鴨長明によって書かれた「方丈記」の書き出しです。世のすべてのものは常に移り替わり、すべては変化していてやがて滅んでいくという仏教の「諸行無常」を表現していますが、今回の参院選、百貨店の栄華の夢、市民生活の変化を見ていますと「水の流れは絶えることはないが、流れる水は同じではない。流れに浮かぶ水の泡は消えたかと思うとまたできて常に変化している。」昔も今も世の中は常に変化し、その対応を間違えると大変なことになりますよと今回の参院選は教訓を残しました。
- アーカイブ
-
- 2025年12月 (1)
- 2025年11月 (1)
- 2025年9月 (1)
- 2025年8月 (1)
- 2025年7月 (1)
- 2025年6月 (2)
- 2025年5月 (1)
- 2025年4月 (1)
- 2025年3月 (4)
- 2025年2月 (2)
- 2025年1月 (1)
- 2024年12月 (2)
- 2024年11月 (3)
- 2024年10月 (10)
- 2024年9月 (17)
- 2024年8月 (19)
- 2024年6月 (1)
- 2024年5月 (1)
- 2024年4月 (1)
- 2024年3月 (2)
- 2024年1月 (1)
- 2023年12月 (1)
- 2023年11月 (1)
- 2023年10月 (1)
- 2023年8月 (4)
- 2023年6月 (2)
- 2023年5月 (3)
- 2023年4月 (2)
- 2023年3月 (3)
- 2023年2月 (2)
- 2023年1月 (3)
- 2022年12月 (6)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (5)
- 2022年9月 (4)
- 2022年8月 (3)
- 2022年7月 (6)
- 2022年6月 (1)
- 2022年5月 (1)
- 2022年4月 (2)
- 2022年3月 (1)
- 2022年2月 (1)
- 2022年1月 (1)