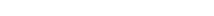更新情報
2025年9月 茶況_No.418
産地情報
令和7年9月29日
茶 況
茶園では、まもなく始まる秋冬番茶摘採の準備を進めています。秋冬番茶の摘採時期と摘採位置が来年一番茶の品質と摘採時期に影響しますので適正な対応が求められますが、今年は猛暑の影響で芽伸びが遅れ例年より1週間遅い10月上旬から本格化します。夏の猛暑と雨不足の影響で全体的に芽伸びが進んでいませんので2~3割の大幅な減産が予想されます。26日に静岡茶市場で秋冬番茶の初荷が史上最高値の1380円で落札されました。前年比約4倍の高騰に買い手からは「いくらなんでも高過ぎる。異常な高値だ」との嘆きの声も聞かれました。「農家の生産意欲が高まるのはいいが、原料高騰で既存商品の一部を廃番にするしかない」と頭を抱えています。二茶に引き続きドリンク関連の需要は旺盛で、今年の相場は例年の2.5倍~3倍の1000円前後の高値観測が広がっています。今年の茶生産は離農と碾茶生産への転換により煎茶向けが品薄になった一方、ペットボトル茶の原料需要は増えて下物茶価格の異常な高騰が続いています。昨年に続き今年も茶商青年団と若手農業者との意見交換会が開催されました。現在置かれている茶業界の危機を乗り越えるのには、どうすればいいのか。茶商と生産者が本音を交わし静岡茶再興の思いを共有しました。茶商側からは「今年の値段では商品の一部を廃番にするしかない。消費者離れが心配だ」との声も出ました。一方、生産者からは「今年の二番茶相場でようやく工場の経営が成り立つ」や「域内の生産者が20年間で800人減り400人に落ち込んだ。内50歳以下は50人。相場うんぬんよりも生産が続けられるか心配だ」との声や「生産者・茶商ともに共存できる体制が必要」との意見もありました。掛川の若手茶商から「静岡茶はずっと一番できて業界が変わる必要がなかった。もう旧態依然では立ち行かない。意欲ある生産者と一緒に変わっていくべきだ」との意見も出ました。
産地問屋は仕上・発送作業を進めながら秋需に備えた販売計画を進め、まもなく始まる秋冬番茶の数量確保と受入れの準備を進めています。既存の緑茶商品や販売ルートに加え、緑茶関連商品や健康茶など、新商品と新販売ルートの販路拡大に努め売上減少傾向からの脱却に懸命です。昨年は年間生産量で静岡は鹿児島に抜かれましたが、今年は一番茶生産量でも初めて首位の座を明け渡しました。一番荒茶の今年の生産量は鹿児島8440トンに対し静岡8120トンです。鈴木康友県知事は、定例会見で「生産量はあくまでも結果、まずは力強い茶業を営んでいけるように構造転換を図り、稼ぐ茶業、強い茶業を目指す。その結果として生産量が増えていく」と述べ、ユニクロや今治タオルのブランド戦略を手掛けた佐藤可士和氏を総合プロデューサーに迎え「世界に通用する静岡茶ブランドづくり」を始動させました。荒茶生産量は鹿児島に抜かれましたが、茶問屋で製茶・包装される「仕上茶」の出荷額は静岡1264億円、鹿児島107億円(2022年)と流通を含めれば静岡の日本一は揺るぎません。30年前に「昇る朝日の鹿児島茶、沈む夕日の静岡茶」と冗談話が出ましたが30年の間に現実になってしまいました。「山は富士、お茶は静岡、日本一」と再び言われるように関係者は退路を断って臨む必要があります。
消費地では「秋の売り出し」の準備と「歳暮商戦」の企画を進めています。家庭でも2ℓペットボトルの需要が増えて、急須で入れるリーフ茶の苦戦が続き売上減少は深刻です。「フィルターインボトル」や「ティーバッグ」を使って作った「自家製緑茶」を冷蔵庫へ保管して飲めばペットボトルより安くて美味しくて地球環境にも良いですよとお奨めします。地域に必要とされるお店、無くなったら困るお店を目指して地域密着で頑張っています。物価高騰が進む中、家計負担が重くのし掛かり、10人に3人が65歳以上の高齢化社会を迎え、その負担も若年層に重くのし掛かっています。家計支援と高齢化対策は急務です。総裁選後の新総理の手腕に期待が集まります。
日本の正義と寛容の精神
自民党総裁選が告示され5氏が立候補しました。野党との政権枠組みの在り方を主要争点に、物価高対策や外国人政策が大きな論点となっています。参院選で大敗を受けた党の立て直しも問われ10月4日に新総裁が選出されますが、国民の閉塞感が払拭できるかは疑問です。党内の「石破降ろし」に伴い政策課題が停滞し10月4日まで政治空白が長期化する見込みです。旧態依然の長老支配と権力闘争、政治とカネ問題に加え、厳しさを増す現役世代から見放されたことこそが自民党が支持を失った根本原因なのに「変われ自民党」を掲げていますが何も変わっていません。三島由紀夫が予見した「政治は矛盾の糊塗、自己の保身、権力欲、偽善にのみ捧げられ、国家百年の大計は外国に委ね・・・」と命を懸けて提起した55年前と何も変わっていません。石破政権が発足してから1年、世論調査では支持率が上昇傾向にある中で「石破降ろし」にあらがえずの退陣は「残念ながら道半ばだ」との無念の言葉も漏れました。実質賃金の低迷による対策として「最低賃金引上」や、米国との「関税交渉合意」、若者や女性に選ばれる「地方創生」などを評価する声も多く、その手腕をもう少し見てみたかったとの声も多く聞かれます。結局は自民党内の権力闘争であり、国民からは理解を得られないのではないでしょうか。訪米してトランプ大統領と日米の今後の在り方を詰め、訪日したインドのモディ首相と日印首脳会談を開催し、訪日した韓国のイ・ジェミョン大統領とは未来志向的な今後の日韓関係の構築を話し合ったばかりでした。こんなにトップがコロコロ変わる国では、世界における日本の立ち位置も確保出来ませんし信用できません。日本政府が主導して大きな成果を上げたのがTICAD「アフリカ開発会議」です。巨大市場アフリカを巡る各国の競争は激化の一途をたどり進出合戦を繰り広げています。各国はアフリカの持っている重要鉱物資源に関心を示し、将来大きく発展するアフリカ域内の貿易需要を狙って足場を作るのが目的です。治安や政情が不安定でもリスクを冒す価値があると中国・ロシアは進出の度を強めています。特に中国が一歩も二歩も先んじている中で日本はどう向き合うべきかを成果文書「横浜宣言」で明確にしました。経済成長支援、産業協力強化、人材育成に取り組む等、ウインウインの関係を発展させることを明記しました。中国の方針とは一線を画し「共に笑い、共に泣き、共に汗を流す」姿勢こそが日本の良さです。巨大市場アフリカは「最後のフロンティア」「宝の山」と呼ばれ、世界各国が進出合戦を繰り広げていますが、昔と違って今はアフリカ側がパートナーを選ぶ時代に入り「日本は一貫して信頼できるパートナーだ」と認めています。中国は「内政不干渉」を掲げアフリカを運命共同体と位置づけて多額の援助を表明し連携を強調しました。ロシアは内戦・内紛の続く貧困国に軍事支援・選挙介入や鉱石採掘を通してアフリカへ執拗に介入しようとしています。日本は中国・ロシアと同じ道を進みません。インフラ整備や人材育成といった分野を重視して、見返りだけを求めるのではなく、長期的な相互利益に重きを置きます。日本が戦後、様々な苦難を乗り越え発展して来た知恵を学びたいとアフリカ諸国は考えています。世界が分断に向かっている今こそ国際社会で日本の立ち位置を明確にする必要があります。国際社会で日本は経済的地位の低下、国力の衰退が指摘されていますが国際秩序が揺らぐ中、新たな方向性を提示して目指す国際社会像を達成するために課題策を各国とともに作っていくことが、日本にふさわしい役割を果たすことに繋がるのではないでしょうか。いま世界的に自由主義や民主主義が崩れ「自国ファースト」を掲げて社会の分断を煽るような言動が増え、排外主義を打ち出せば支持を広げやすい風潮が蔓延しています。法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序は歴史的な挑戦を受けています。石破首相は国連で「分断より連帯」「対立より寛容」のメッセージを送りました。そして、健全で強靭な民主主義を守り抜くことを世界に宣言しました。今、米国・中国・ロシアといった国々と心底から向き合う国はないでしょう。自国の利益だけだからです。分断と対立を煽るからです。世界は日本が正義と寛容の精神を持って立ち上がってくれることを期待しています。その期待に今こそ答える必要があります。
- アーカイブ
-
- 2025年9月 (1)
- 2025年8月 (1)
- 2025年7月 (1)
- 2025年6月 (2)
- 2025年5月 (1)
- 2025年4月 (1)
- 2025年3月 (4)
- 2025年2月 (2)
- 2025年1月 (1)
- 2024年12月 (2)
- 2024年11月 (3)
- 2024年10月 (10)
- 2024年9月 (17)
- 2024年8月 (19)
- 2024年6月 (1)
- 2024年5月 (1)
- 2024年4月 (1)
- 2024年3月 (2)
- 2024年1月 (1)
- 2023年12月 (1)
- 2023年11月 (1)
- 2023年10月 (1)
- 2023年8月 (4)
- 2023年6月 (2)
- 2023年5月 (3)
- 2023年4月 (2)
- 2023年3月 (3)
- 2023年2月 (2)
- 2023年1月 (3)
- 2022年12月 (6)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (5)
- 2022年9月 (4)
- 2022年8月 (3)
- 2022年7月 (6)
- 2022年6月 (1)
- 2022年5月 (1)
- 2022年4月 (2)
- 2022年3月 (1)
- 2022年2月 (1)
- 2022年1月 (1)