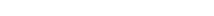更新情報
2025年10月 茶況_No.419
産地情報
令和7年11月5日
茶 況
秋冬番茶の摘採が終了した茶園では、来年の一番茶に向けた秋の茶園管理が進められています。夏の水不足と猛暑による生育不良から樹勢の回復を一番に管理に努めます。これから冬にかけて茶園の畝間に乾燥させた山草を敷き詰めていきます。今年最後の製造となる秋冬番茶はドリンク需要に支えられて、昨年は350円が今年は1400円~1500円で取引され昨年の4倍という異常な高値で終了しました。長年の茶価低迷による離農者の続出、気候変動による減産、需要変化に伴う碾茶への生産転換により3割前後の減産となり、ドリンク関連業者が必要数量の確保に動いたことが相場形成の大きな要因です。2025年の茶園面積は静岡県11.600ha(1200ha9.3%減)鹿児島県8.040ha(110ha1.3%減)と静岡県が生産者の高齢化と茶価低迷により離農が進んだことが茶園面積の減少に大きく関わっています。一方、放棄茶園を再整備して碾茶生産やレモン栽培に切り替えて活路を見い出している生産者もいます。減産と碾茶への生産転換で秋冬番茶の流通量が例年以上に減少し、ドリンク関連の数量確保の動きに繋がっていますが、この状況は今後も続くと関係者は話します。静岡県は昔から相対取引が多く荒茶価格1400円~1500円で推移しましたが、鹿児島県茶市場は高値落札による入札販売のため2000円~3000円と高騰が収まる気配はなく、静岡を上回る相場が続きました。過去にない高値に「この値段ではついていけない、手を出せない水準まで来ている」や「コメの高騰どころではない、ここまで上がると資金繰りができない」と嘆きの声も聞かれます。今年製造されたすべての原料が県内各問屋の冷蔵庫に収まりましたが、この原料が順調に出荷されていくのか、今年ほど不安を抱えての需要期入りは記憶にありません。
コメの不足感から価格が高騰した「令和の米騒動」国が需要量の増加を見誤って供給不足を招いたことが原因と結論付け小泉農相は増産を打ち出しましたが、高市政権で新たに就任した鈴木農相は2026年の生産量を711万トンと減らす方向で動いています。2025年の収穫量748万トンからは大幅な減産となりますが、供給過剰で価格が下落するという生産者の心配に配慮した政策の一環です。小泉農相は備蓄米の放出で市場に積極的に介入しましたが、鈴木農相は「政府が価格にコミットするべきではない」と真逆の方針で、価格は需要と供給に応じて市場で決まるとの立場で備蓄米による価格抑制には反対しています。お米もお茶も消費者が納得いく施策が求められています。
静岡茶入札販売会は60社が参加、総落札額1650万円(前年比533万円増)落札率は鶴印5000円が50%(前年45%)亀印3000円が79%(前年48%)とまずまずの結果でした。各問屋は新市場・新販売ルートの開拓など販路拡大に努め縮小傾向の構図脱却に懸命に努力します。経営姿勢とターゲットの方向性により問屋間の格差も広がっています。消費地では「秋の売り出し」と並行して「歳暮商戦」の準備に入っています。急須で入れるリーフ茶需要の低迷が続き厳しさは続きますが、地元に愛されるお店「あのお店のあの商品をあの人から買いたい」と言われるように頑張っています。昨年までは生産者から「この状況が続くなら、もうやっていけない」と離農を選択する生産者が続出しましたが、今年は「この価格では経営が継続できない」と廃業を選択する産地問屋・消費地小売店が続出しそうです。お互いにどうしたら生き残れるのか、茶業界も大きな転換期を迎えています。
打って反省 打たれて感謝
日本の歴史上初の女性首相が誕生し自民と維新の連立政権の枠組で高市内閣が発足しましたが政権は多難な船出となりました。少数与党で政策実現には野党の協力が不可欠な状況は変わりません。政策を進めるには、いずれかの野党の賛成を得る必要があります。生産性や賃金を上げる重要性は与党も野党も分かっているわけですが考え方や進め方が違います。今までは議論は小手先の話が主流で不満が出ないように、目先の分配をどううまくやって票を取るかが中心でした。目指す政策をどうしたら達成・継続できるのかを真剣に国会で議論することが必要です。高市首相の所信表明演説では、強くて豊かな国家づくりをしたいとの思いは伝わってきますが、巨額の財源はどうするのか、国民に負担を求めるのか、企業に負担を求めるのか、赤字国債を発行するのか、政権が軌道に乗るまで注視します。「物価高対策」「経済対策」「外交政策」「安全保障」を主な柱に「日本列島を強く豊かにして、日本を再び世界の高みに押し上げてまいります」と宣言しました。その力強さに高市内閣の支持率は小泉内閣、鳩山内閣に次ぐ3番目の68%と上昇し東京株式市場も大幅に続伸して日経平均株価が5万円を突破しました。日米・日韓・日中の会談も順調な 滑り出しでトップ同士の信頼関係の構築が出来ました。日本はいま人口減少と高齢化が進み構築してきたシステムが根本から崩壊しそうな難局に直面しています。優先的に取り組むテーマを決めて進まなければ日本は衰退の一途です。本当に変われるのかのラストチャンスを迎えていると言っても過言ではありません。「日本がいないと成り立たない」と世界で言われる得意分野をいくつ作れるかが日本成長のカギを握っています。そのためにも、この先10年、20年、日本企業がどの分野で食べていくのか勝ち筋を見極めなければいけません。高市首相は所信表明演説で、国際秩序はパワーバランスの歴史的変化と地政学的競争の激化に伴い大きく揺らいで軍事的動向等が深刻な懸念になっていると指摘しました。ウクライナで続く戦争や中東情勢など世界では待ったなしの決断を迫られています。ヨーロッパで起きている極右政党の躍進は「自国第一主義」「反移民」を掲げ、対立と分断を生み、格差社会はますます広がりつつあります。所信表明演説では「世界が直面する課題に向き合い、世界の真ん中で咲き誇る日本外交を取り戻してまいります」との決意を述べましたが、世界は日本のその行動に期待しています。
剣道の教えに「打って反省、打たれて感謝」の教えがあります。何故、打って1本取ったのに反省するのか?何故、打たれて1本取られたのに感謝するのか?打って1本取った時にもその1本が正しい打突だったのか自己反省をする。打たれて1本取られた時には自分の弱点と隙を教えてくれた相手に感謝の気持ちを持つことを意味します。自分の行動を常に反省して相手に敬意を払う精神は、日本が古来から礼節や精神的修養を重んじる「道」の文化を大切にしてきたからです。世界はいま「戦争と紛争」「対立と分断」など火種となる懸案に溢れ「打って自慢と誇示、打たれて激怒と報復」が当たり前になっています。超大国の米国・中国・ロシアと表向きは接しても、自国の都合ばかりを優先して力で押さえる国と心底から向き合う国はないでしょう。日本には「道」を大切にする精神と超大国にはない信用と信頼があります。コロンビア大学のブラッドフォード教授は「私は仕事で世界中を巡るが、日本を好きではないという人に出会ったことがない。日本には優秀な人物が豊富に存在し、優れた大学も資金力もある科学技術立国です。日本こそが人材の目的地になり得る可能性があり、世界をリードする国のはずです」と語っています。日本が世界の相互利益に重点を置き、平和の誓いを継承して世界の安定と繁栄に貢献して、高市首相が目指す日本外交が世界の真ん中で咲くことを世界は期待しています。
- アーカイブ
-
- 2026年1月 (1)
- 2025年12月 (1)
- 2025年11月 (1)
- 2025年9月 (1)
- 2025年8月 (1)
- 2025年7月 (1)
- 2025年6月 (2)
- 2025年5月 (1)
- 2025年4月 (1)
- 2025年3月 (4)
- 2025年2月 (2)
- 2025年1月 (1)
- 2024年12月 (2)
- 2024年11月 (3)
- 2024年10月 (10)
- 2024年9月 (17)
- 2024年8月 (19)
- 2024年6月 (1)
- 2024年5月 (1)
- 2024年4月 (1)
- 2024年3月 (2)
- 2024年1月 (1)
- 2023年12月 (1)
- 2023年11月 (1)
- 2023年10月 (1)
- 2023年8月 (4)
- 2023年6月 (2)
- 2023年5月 (3)
- 2023年4月 (2)
- 2023年3月 (3)
- 2023年2月 (2)
- 2023年1月 (3)
- 2022年12月 (6)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (5)
- 2022年9月 (4)
- 2022年8月 (3)
- 2022年7月 (6)
- 2022年6月 (1)
- 2022年5月 (1)
- 2022年4月 (2)
- 2022年3月 (1)
- 2022年2月 (1)
- 2022年1月 (1)